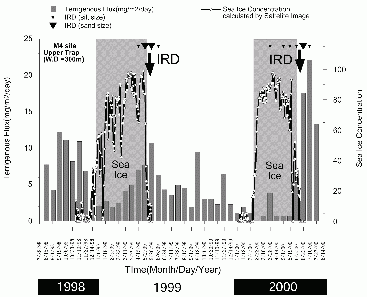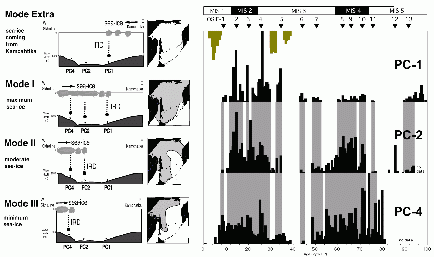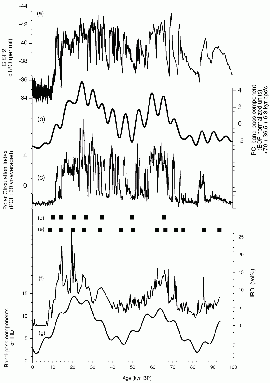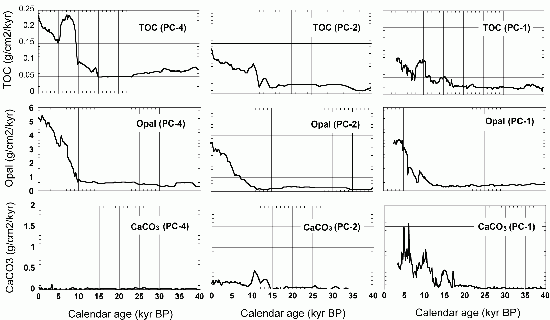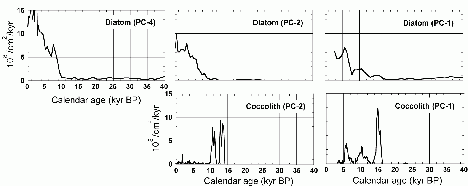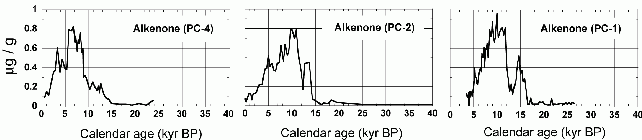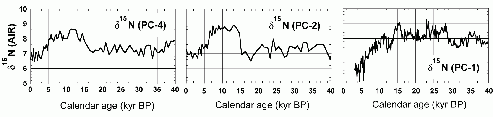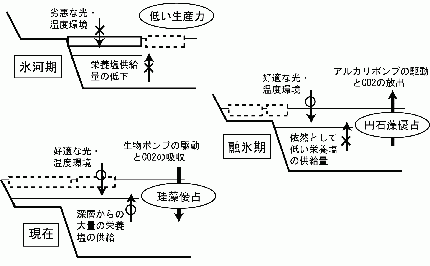|
オホーツク海は、北部北太平洋、ベーリング海などと共に、現在は「シリカの海」であり、珪藻が大繁殖する特徴を共有している。オホーツク海における古生物生産の復元は、それ故、単にオホーツク海内部に留まらず、広く北部北太平洋全体での炭素循環を解析するために、大きなヒントを与えてくれる可能性がある。
図4.6.5に、PC−4,
2,
1コアの中の生物起源成分である、全有機炭素(TOC)、非晶質シリカ(Opal)、炭酸カルシウム(CaCO3)の過去4万年間にわたる堆積フラックスの変化を示す。ここで、OpalとCaCO3の経年変化は、それぞれ植物プランクトン化石である珪藻、円石藻のフラックスの歴史的変化(図4.6.6)に対応しており、それぞれの生物生産量を表すProxyであることが分かる。CaCO3のフラックスは、オホーツク海西部のPC-4コアでは、過去4万年間を通して一貫して低く、円石藻の化石もPC-4コアには全く含まれていなかった。しかし、同時に測定された円石藻のバイオマーカーであるアルケノン(図4.6.7)は、PC-4においても、融氷期に高い変動パターンを示している。このことは、PC-4地点でも、円石藻の生産は他の2地点と同様に生じていたが、円石藻を構成していたCaCO3の殻が、堆積後、この地点では溶解してしまっていたことを意味している。原因としては、PC-4地点の堆積速度が他地点と比べて速いため、有機物分解起源のCO2などの酸性物質が、堆積物の間隙から底層水へと拡散排出されにくく、共存するCaCO3粒子を溶解させてしまったこと等が考えられる。
オホーツク海の植物プランクトン生産量・群集組成の歴史的変遷には、以下のような特徴が見て取れる。1)TOCで代表される生物生産量は、オホーツク海全体で、氷河期(最寒期は、21,000年前)に低く、融氷期(18,000年前〜10,000年前頃)〜間氷期(完新世
: 過去1万年間)に高い、2)Opalで代表される珪藻の生産量は、氷河期〜融氷期を通じて低く、完新世中期の約6,000
年前以降になってから急速に増大する。
3)CaCO3に代表される円石藻の生産量は、氷河期にはきわめて低いが、融氷期の約15,000年前頃から急速に増大し、完新世前期まで高い値を維持し、それ以降急速に減少する。空間的には、円石藻の生産量は、オホーツク海東部(PC-1地点)でより多く、また融氷期における生産量の増大も、東部海域でより早く起っているが、生産量が減少し始めるのは、オホーツク海西部(PC-4)で一番遅く、約3,000年前まで、西部海域では円石藻の生産が多かった。円石藻の生産には、同じ融氷期の中でも2つの大きな増大時期が認められる。これは、融氷期に2回に分けて起ったグローバルな氷床の融解イベント(Melt
Water
Pulse:MWP-1とMWP-2)に時期的に、ちょうど対応している。興味深いことに、各堆積物コア毎に、Opalの変動パターンと、CaCO3(もしくは、アルケノン)の変動パターンを重ね合わせてみると、TOCの変動パターンに極めてよく一致することが分かる。このことは、オホーツク海の過去4万年間において、珪藻と円石藻が、お互いに拮抗するレベルの一次生産を、交互に生み出してきたことを、示唆している。
以上、まとめると、まず「氷期」には、珪藻の生産量は現在より少なく、一方、円石藻もほとんど存在しなかった。「融氷期〜完新世前期」には、円石藻の大繁殖が生じたが、珪藻は相変わらず現在より生産量が少なかった。「完新世中期以降」に、オホーツク海の植物プランクトンの種組成は、一変し、円石藻が衰退し、珪藻の生産量が非常に大きくなってくる。つまり、現在、当たり前のように見られている「珪藻の海」としての特徴が、オホーツク海にもたらされたのは、数千年前に過ぎず、それ以前の融氷期−氷期のオホーツク海は、生産量、種組成の両面において、現在と極めて異なる世界であったことが分かる。
|