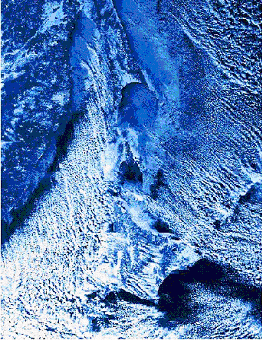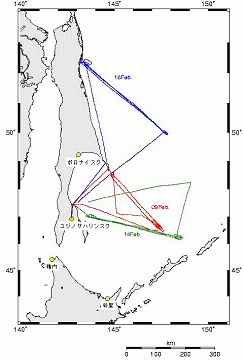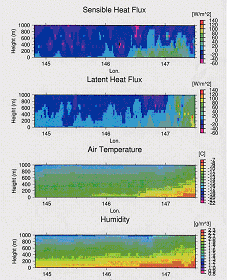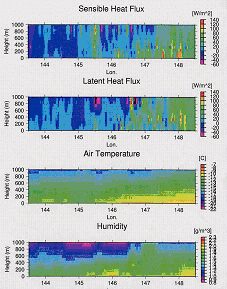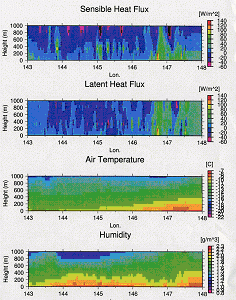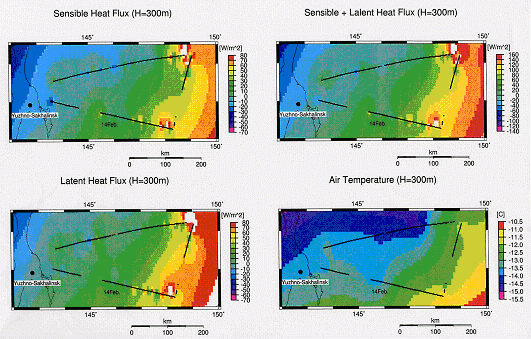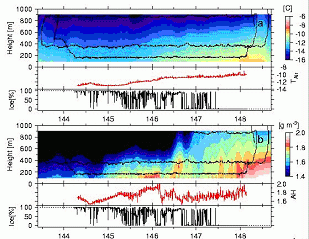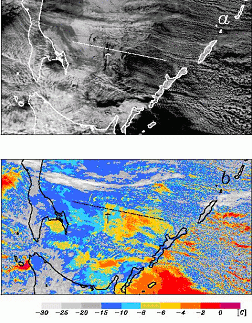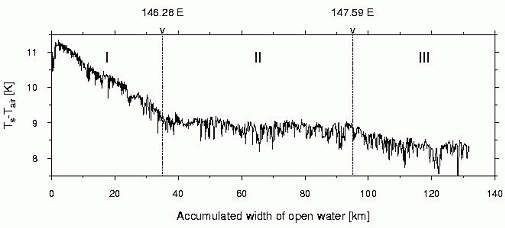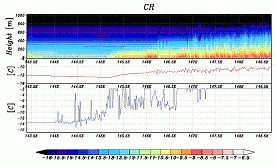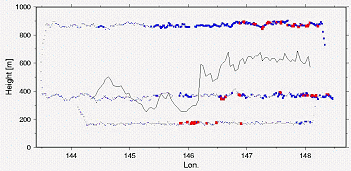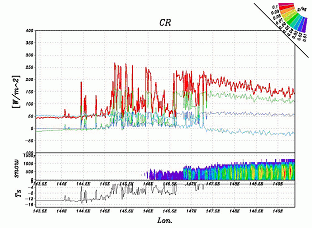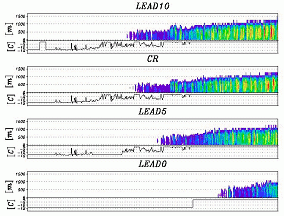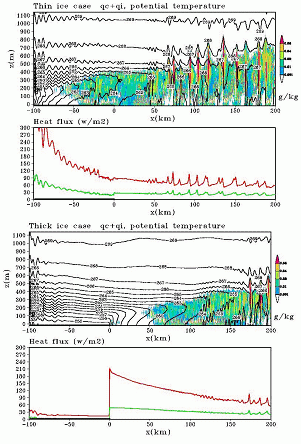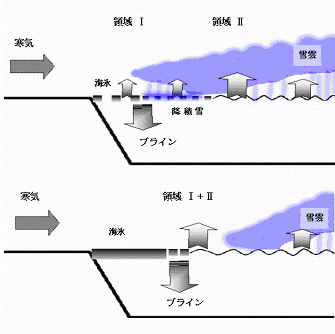|
海氷域に存在するリードが大気の加熱に及ぼす役割をより定量的に示すために、海氷密接度を陽に扱った2次元の雲解像モデルを用いて、気団変質およびそれに伴う雲の発達のシミュレーションを行った。計算はオクラホマ大学で開発された非静力学大気モデルARPS
(Advanced Regional Prediction System) (Xue et al.,
1995)を用いた。モデル領域は水平方向に400km、鉛直方向に8.6kmとり、格子間隔は水平方向が500m、鉛直方向には最下層で25m、上層で330mとストレッチさせた。領域は2月14日のIL-18の飛行経路を想定している。初期の温度場と湿度場はIL-18による鉛直方向の観測で得られた値を一様に与えたが、風速については10m/sで全層一様とした。下部境界のデータは、前節で述べた画像解析で得られた海氷密接度から、開水面あるいは氷面を判断して与えた。格子間隔は水平500mとしているが、実際はそれよりも小さいスケールで海氷と開水域とが共存している部分もある。その効果を計算に反映させるため、赤外線カメラによる観測で得られた500m平均の密接度ICと海氷面の温度TRを用いて、各グリッドに与える温度
Tsは以下の式で与えた。
Ts=(1-IC)×(-1.8)
+ IC×TR
なお、開水面の温度は-1.8度(結氷温度)と仮定し、潜熱フラックスは密接度が0%の場所は開水面、それ以外は100%氷で覆われているものとした。このため、潜熱フラックスは過小評価されることになる。
数値実験の結果(12時間後)を図4.5.8に示す。上段は気温,中段は下層(高度175m)の気温,下段は前述の式で与えた下部境界の温度である。
気温は海氷に覆われた領域で緩やかに低下し、観測と同様リードが現れる145.3E付近で急激に上昇し始める。
146E付近から147.4Eまで混合層の厚さが増加しているが、この間は下層の気温が殆んど上昇していないことが分る。図4.5.9は、可視ビデオカメラの画像上で、飛行経路上に雲が存在した地点と降雪粒子が確認された地点、及び、最下層の空気の持ち上げ凝結高度を示したものである。降雪をもたらす雲は146E付近から現れているが、そこで凝結高度も急激に上昇していることがわかる。このことから、146E付近での雲の発達に伴って対流混合が活発になったことが示唆される。図4.5.10は、同じ数値実験の結果であるが、上段は高度175mでの熱フラックスで、赤線は正味の上向き熱フラックス、緑線は顕熱、青線は潜熱、水色の線は正味の放射熱フラックスの水平分布を、そして中段には雪水量(g/kg)と下段に海面温度の水平分布を示したものである。この図からも分るように、降雪をもたらす活発な雲は観測とほぼ同じ場所から現れており、そこから急激に対流混合が活発になっている。
すなわち海面付近で温められた空気が上に運ばれることで気温の上昇が抑えられていると言える。その後、気温は緩やかに上昇し、最終的に気温は2度程度上昇する(図4.5.8参照)。この数値実験は前出の観測結果(図4.5.6)を良く再現しているといえる。
興味深いのは、145Eから146.5EのMIZでは、リード上空で間欠的に大きなフラックスが見られ、大気と海面との温度差が大きいため、フラックスのピーク値は146.5E以降の海水面よりもむしろ大きいことである。更に、146.5Eより風下の開水面での上向き熱フラックスは海氷域の約4倍程度と大きいが、風下に向かって次第に減少している。これは大気と海洋間の温度差の減少に伴う顕熱フラックスの減少だけでなく、雲からの下向き赤外放射の増大(図では負の値が増大)に起因する。
次に、海氷域に存在するリードが大気の加熱に及ぼす影響をより定量的に示すため、下部境界の条件を変えて3種類の実験(LEAD10,LEAD5,
LEAD0)を行なった(図4.5.11)。LEAD10は上流の開氷域に10kmの開水面を加えた実験。LEAD5は、上流部の5kmの開水面を氷面に変えた実験。LEAD0は上流部の開水面を全て氷面に変えた実験である。CRは前出の実験結果である。それぞれの図の上段は雪の混合比(g/kg)、下段は下部境界の温度を示している。図4.5.11から明らかなように、開水面が風上に数多く存在する程雲がより風上で形成され雪が降る。先に述べたように、雲が形成されると、雲からの下向き赤外放射が増加する。また、図には示さないが、風下(149E)での上向き熱フラックスはコントロールラン(150W/m2)に比べ、風上の海氷域の開水面を加えたLEAD10は10W/m2小さく、逆に開水面を減らしたLEAD5は10W/m2大きくなり、海氷域の開水面をなくしたLEAD0に至っては30W/m2上向き熱フラックスが増加した。すなわち、風上に存在する小さな開氷域での大気の温度上昇によって氷縁域での顕熱と潜熱フラックスは減少し、さらに雲からの下向き長波放射により氷縁域の海水はより冷えにくくなると言える。この雲の効果は、顕熱と潜熱フラックスの風下方向の減少と合わせると、氷縁域での正味上向き熱フラックスの減少をもたらし、気団変質(あるいは海面の冷却)の負のフィードバックとなる。すなわち、海氷域の拡大期に、ポリニア及び無数の氷の割れ目での気団変質とその結果生じる雲システムは、風下の氷縁域での海氷生成とそれによる海氷領域の拡大を抑制することが示された。
上では、海氷域に存在するリードの役割を、モデルを用いて議論した。一方、本来海氷は海洋と大気間の熱交換を遮断する役割をもつが、その効果は海氷の厚さに依存する(例えば、Maykut,
1978)。
海氷が薄いと、海氷の上でも緩やかではあるが気団変質が起こる。オホーツク海南西部で行われた2000年2月14日の観測領域は、極域に比べ氷厚が薄いオホーツク海の中でも比較的厚い氷が卓越するが、表面熱収支にとって海氷からの上向き乱流熱フラックスも重要であることがInoue
et al.
(2001)によって指摘されている。
そこで次に、海氷の厚さに関連して生じる海氷上での気団変質の大小が、MIZでの局所的な冷却(潜熱・顕熱フラックス)や雲の発達にどのような効果を与えるかを数値実験によって調べた。すなわち、上記のLEAD0のケースと同様に、風上100kmの領域をすべて海氷で覆い、それより風下側をすべて海面として数値実験を行なった。海氷面の温度は海氷が厚い場合
(Thick Ice)と薄い場合(Thin
Ice)を想定してそれぞれ-18度、-6度とし、海面の温度は両者とも-1.8度としている。大気の温度は最下層が-18度で初期に200mの厚さの接地逆転層がある場合を想定している。
図4.5.12
に示した計算結果を見ると、海氷が薄い場合は、海上に出る前に気団変質が起こってしまうために大気との温度差が解消され、海洋上での顕熱フラックス(緑色の線)、潜熱フラックス(黄色)ともに小さくなっている。これは、海氷域で雲や降雪が生じていることからも分かる。これに対し、海氷が厚い場合は海洋上で急激に気団変質が起こる。一方、海氷が薄い場合には、海氷上で既に雲が発生しかつ降雪も生じているが、海氷が厚い場合には、氷縁から数10km風下で雲と降雪が発生している。また、興味深いのは雲底高度の変化である。海氷が薄い場合の計算結果で顕著であるが、雲は高度200m付近に発生し、風下にいくにつれて雲頂が上昇すると同時に雲底も下がりほぼ地表に達する。これは、CAOのパイロットからの目視観測結果と一致する。その後海上風下で対流が活発になると、今度は逆に雲底高度が上昇し、これも図4.5.9に示した観測結果と一致する。雲底下で相対湿度が下がることによって、降雪粒子は雲底下で蒸発し下層の空気を冷却する。 |