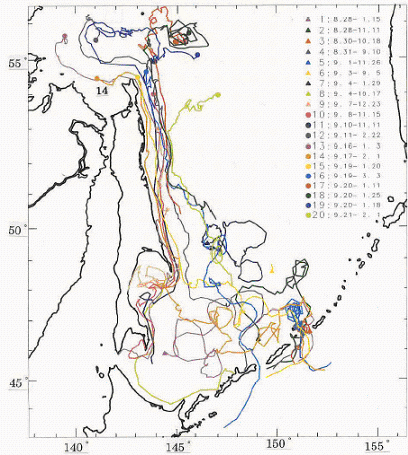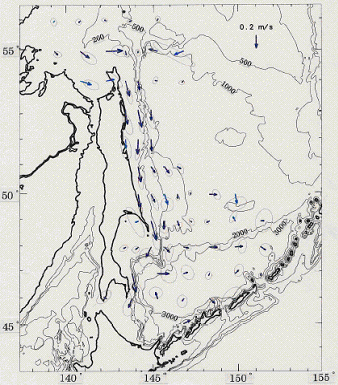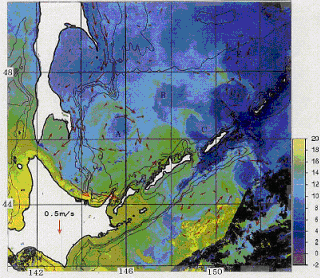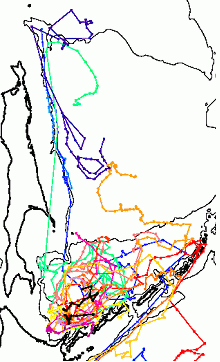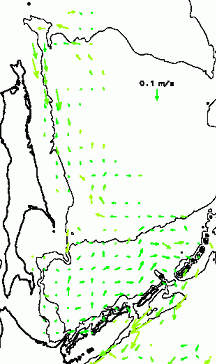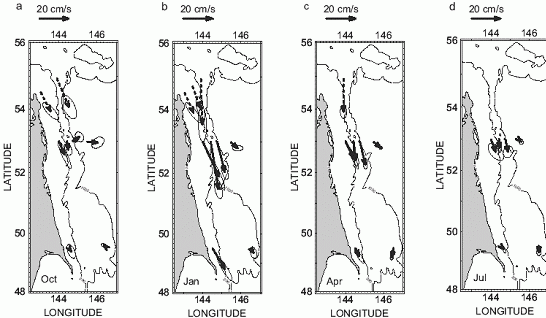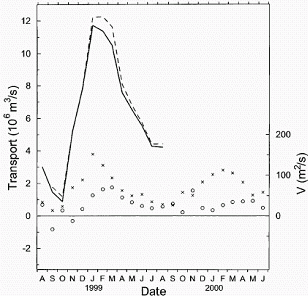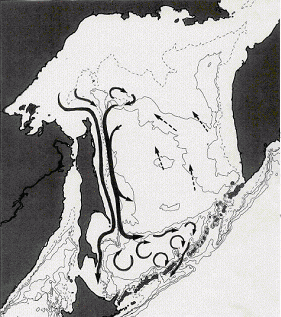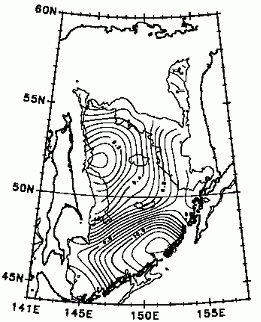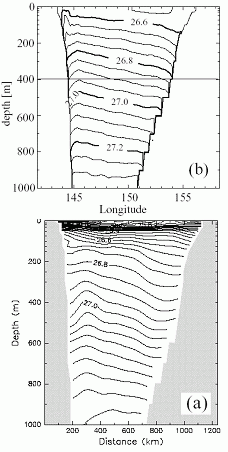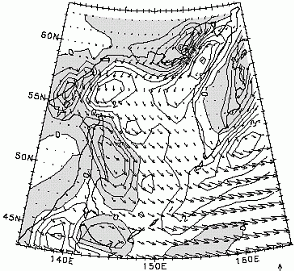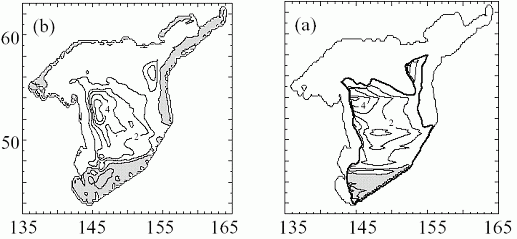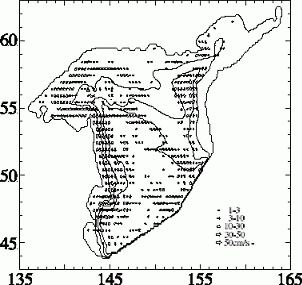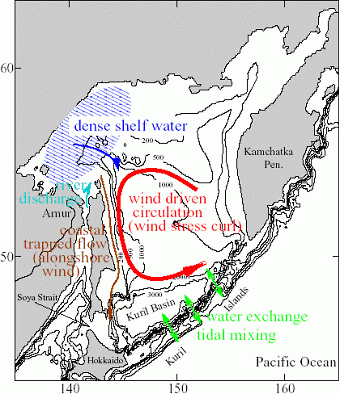1999年8月〜9月にロシア極東気象水文研究所のProf. Khromov号により計20個のアルゴス表層ドリフターが投入された。図4.2.1は全ドリフター20個の軌跡を示したものである。最も顕著な特徴は東樺太沖の等深線に沿う南下流すなわち東樺太海流の存在を明確に示している点である。ドリフターは樺太北端からテルペニア湾までは約1ヶ月かけて南下し、その後は2つのグループにわかれる。1つのグループは岸近く等深線に沿ってさらに南下し北海道沖まで向い、もう一つのグループは北緯48-52度あたりで東へ向い千島海盆へ入っていく。東進して千島海盆に入ったものの軌跡から、この海盆には直径100-150km程度のメソスケール渦(ほとんどが高気圧性)がいくつも存在していることが示唆される。オホーツク海内で生き延びたドリフターはすべて6ヶ月以内に太平洋へ流出したが、そのほとんどがブッソル海峡から流出している。これらのことから、(ドリフターが主に投下された)千島海盆や東樺太陸棚上の表層水はオホーツク海において少なくとも1年以内の滞留時間しか持たないこと、そしてブッソル海峡がオホーツクの表層水が太平洋へ抜ける主な出口となっていること、が示唆される。
1つのドリフターから1日20-30回の位置データが取得できる。この位置データ適当なデータ処理(品質管理)を施し、位置データの差から各ドリフターごとに流速ベクトルの時系列を計算する。さらに平均流成分(25時間平均)と潮流成分(生―平均)に分離する。これらのデータを用いて以後平均流と潮流について解析を行った。
図4.2.2は、全ドリフターデータを用いて緯度方向に1度、経度方向に1.5度(約100km)のボックスごとに、平均流を求めたものである。但し、東樺太沖では、経度方向には半分の0.75度で分解している。矢印の先の楕円は、各流速成分の分散、データ数、及びラグラジアン時間スケールから95%の信頼度での誤差楕円を示したものである。
図4.2.2の結果は過去のスケマティックな流速分布と矛盾ないものとなった。東樺太海流は、少なくとも観測期間中(9-12月)は有意にほぼ定常な南下流として、0.2-0.3m/sec程度の速さを持って存在していることがわかる。図4.2.2からも東樺太海流は樺太南端まで南下する成分とテルペニア湾あたりで東向する成分にわかれることが示唆される。この東向流は0.1m/sec程度であり、東樺太海流とともにオホーツク海中北部の低気圧性循環を作っていると考えられる。オホーツク海の西部に投下されたすべてのドリフターが南下する事実は、東部にはそれを補償する北上流が存在することが予想される。