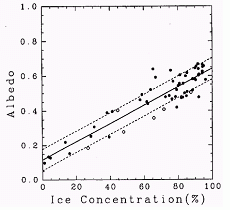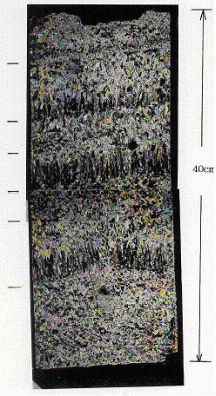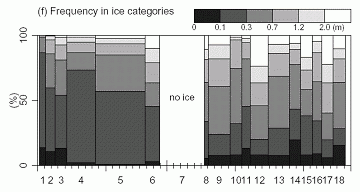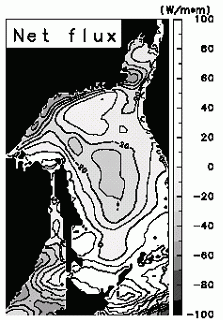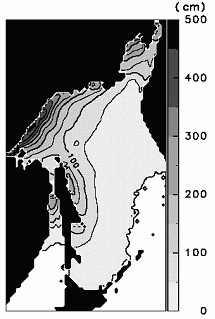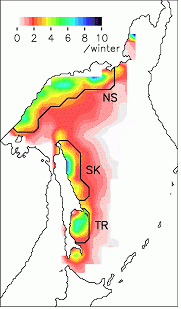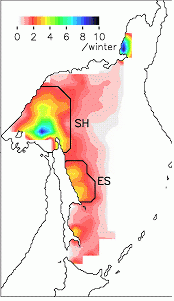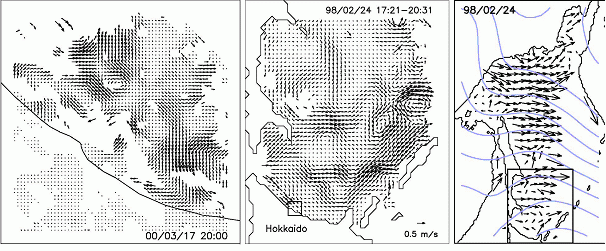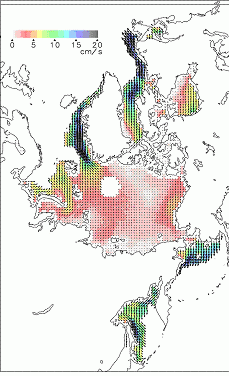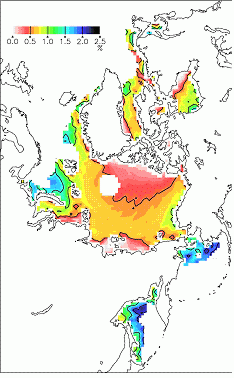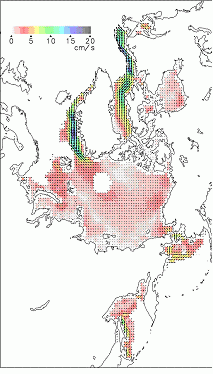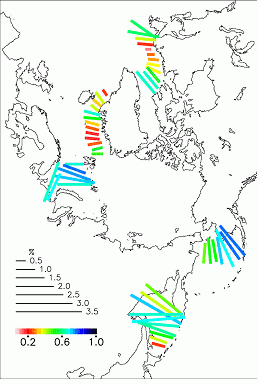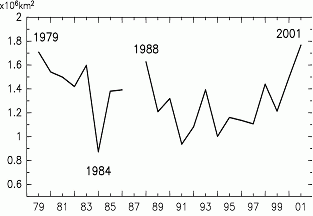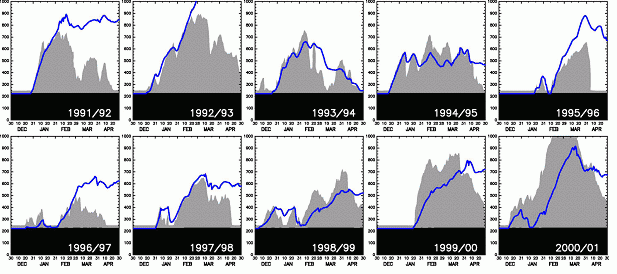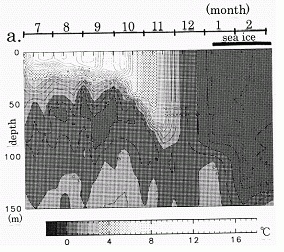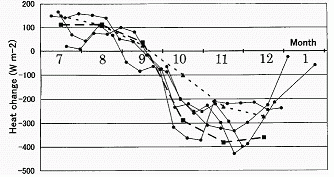オホーツク海の特徴は、何と言っても海氷が存在することにある。しかし、その実態はよく分かっていない。そこで、本研究では、北部海域から南下する海氷の終着域である南部北海道沖の海氷域を季節海氷の一つのモデル海域と位置づけ、砕氷パトロール船「そうや」を用いた現場観測を、1996年から毎年2月に水路部と共同で実施してきた。このような、同じ海域で同時期に現場観測を継続して実施している例は世界的にもほとんど無く、極めて貴重な観測データセットが得られている。
その一例として、海氷のアルベドの観測結果を図4.1.1に示す。海氷のアルベドは、海氷域の熱収支を議論する上で非常に重要な量であるが、世界的にもあまり観測例は無く、オホーツク海氷については勿論最初のデータである。オホーツク海氷アルベドは、年による氷況の違いに関係なくほぼ一定値0.64であることが分かった。極域沿岸定着氷の値(0.75)よりやや小さいのは、低緯度季節海氷特有の雪粒子を多く含んだ、凹凸の激しい表面状況にあることが主因と考えられる。また、各気象要素や氷況観測データ用いて、南西部海氷域全体の熱収支を計算したところ、海洋は熱源になっており、1日あたりの平均海氷成長量は0.5cm以下であり、海氷の現場生産はほんのわずかで、厚い海氷のほとんどは北から運ばれてきたものであることが示唆された。
一方、ビデオによる海氷厚観測結果から、北海道沿岸沖に到達する海氷のうち表面が平らな氷盤については、年による変動はあるものの、平均0.2m−0.6mのものから成っていることが分かった。しかし、これは、あくまで平らな氷盤についてであり、オホーツク海氷の特徴は、南極海氷同様雪を多く含み、さらには氷盤どうしの衝突・重なり合いなど活発な力学過程を経たrafting iceやpressure ridgeなどのいわゆる厚みのある氷盤の割合が圧倒的に多いことなどが挙げられる。図4.1.2は、「そうや」船上から採取した海氷サンプルの鉛直断面である。北から漂流してくる海氷の多くは、このように典型的な構造の海氷盤が数枚重なったものから構成されている。また、北から漂流してくる海氷野のいわば終着地とも言える北海道湧別沖で毎冬実施している係留系による氷厚観測からも平らな数十cmの氷盤よりも数mの厚い(これまでには最大17m)氷盤の割合の多いことが示されている(図4.1.3)。このように、オホーツク海の海氷野は、大小様々な開水面、薄い氷、凹凸の激しい海氷など非常に複雑な表面状況で成り立っていることが示唆された。
次に、オホーツク海全域にわたる海氷の実態については、主として、リモートセンシングや熱収支解析の手法を用いて明らかにしていきたい。